【青色申告は自力で出来る?】やり方や帳簿の仕方、リスクやデメリットを解説!【※税理士監修】
青色申告は自力で出来る?
【やり方・リスク・デメリット】
今回は、『青色申告は自力で出来るのか?』について、青色申告のやり方や注意点、自力でするリスクやデメリットなど詳しく解説させて頂きます。
青色申告は最大65万円の特別控除もある節税効果の高い制度です。
しかし、個人事業主や副業を始めたばかりの会社員の方の中には「本当に自力でできるのかな…」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
青色申告にはさまざまなメリットがある一方で、複雑な帳簿付けや手続きの準備などが必要であり、また、申告ミスや申請遅れで控除が受けられなくなるなどのリスクもあります。
そこで今回は、青色申告は自力で出来る?という疑問に関して、
- 青色申告を自力でするリスクやデメリットは?
- 青色申告のやり方、必要な書類、注意点は?
- 青色申告は会計ソフトなしでも可能?
- 青色申告でおすすめのツールやサービスは?
など、青色申告を初めてされる方、自力で進めるか悩んでいる方などに向けて分かりやすくまとめてみました。
このページで分かる事
青色申告とは?自力でできるのか

青色申告を自力でできるかを判断するために、まずは、青色申告の仕組みや白色申告との違い、利用できる人の条件など青色申告の基礎知識を理解しましょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の最大の違いは、控除の金額と提出すべき帳簿の種類です。
青色申告では、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられる代わりに、複式簿記による帳簿作成や事前申請が必要です。
一方、白色申告は簡易な帳簿で申告できるものの控除額はありません。
青色申告の特別控除を受けるには「期限内に申請し、正しい帳簿を備えていること」が条件とされています。
帳簿の作成や提出が少し複雑になる分、節税効果が大きいというのが青色申告の特徴です。
例えば、年収300万円のフリーランスが青色申告で65万円の控除を受けた場合、課税所得が235万円に減り、数万円単位で税負担が軽くなります。
白色申告ではこれがゼロになるため、同じ収入でも税額が変わってきます。
つまり、しっかりと準備すれば、青色申告の方が節税面では圧倒的に有利と言えます。
青色申告ができる人の条件
青色申告は誰でもできるわけではなく、以下のような所得がある人が対象となります。
- 事業所得(フリーランス、個人事業主など)
- 不動産所得(アパート経営など)
- 山林所得(林業収入など)
さらに、「青色申告承認申請書」を税務署に提出して税務署の承認を受ける必要があります。
この申請は原則として、青色申告を始めたい年の3月15日までに提出しなければなりません(開業したばかりの人は開業から2ヶ月以内が目安です)。
事業としての継続性があれば「事業所得」として青色申告が可能になります。
ただし、単発のバイト収入などは雑所得に該当するため、青色申告の対象外になる可能性があります。
青色申告をするには、収入の性質や継続性、申請のタイミングなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
個人事業主・フリーランス・副業会社員も対象?
副業で収入を得ている会社員の方でも、副業収入が「事業所得」として認められれば青色申告は可能です。
例えば、副業でウェブ制作をして年間50万円以上の継続的な売上があるようなケースでは、「継続性」「営利性」があると判断され、事業所得として認められる可能性があります。
一方で、たまにメルカリで不用品を売った程度では、雑所得扱いになり青色申告はできません。
副業でも真剣に取り組んでいて、将来の利益を見込めるなら青色申告は選択肢に入るということです。
会社員であっても副業収入が一定以上あれば、節税のメリットが得られる青色申告を選んで損はないでしょう。
青色申告を自力でするリスクとデメリット

青色申告は、記帳方法や申告手順を誤ると控除が受けられなくなる可能性もあります。ここでは、青色申告を自力でするリスクとデメリットについて詳しく解説します。
青色申告特別控除が受けられない可能性
青色申告には最大65万円の特別控除という大きなメリットがありますが、これは「帳簿の正確な作成」と「期限内の申告」が条件です。
帳簿の形式や保存期間、提出先などに不備があると控除そのものが適用されません。
例えば、複式簿記で帳簿をつけていても、e-Tax以外で提出した場合は65万円控除は適用されません。
また、10万円控除についても、必要な帳簿を揃えていなかったり申告期限を過ぎていたりすれば対象外になります。
誤った経費計上によるリスク
青色申告では経費を差し引いて課税所得を減らせますが、計上ミスは大きなリスクになります。
よくあるのは、自宅の光熱費や家族での外食代などを「必要経費」として全額計上してしまうなど、プライベートな支出を事業経費として処理してしまうケースです。
「家事按分」の扱いが曖昧なままだと税務調査で指摘され、追徴課税の対象になることもあります。
税務署から指摘・修正を求められるケース
帳簿の整合性や記帳ルールに不備があると、税務署から「確認のための呼び出し」や「修正申告の指示」を受けることがあります。
税務調査のように大規模なものではなくても、内容の再提出や説明を求められると精神的にも時間的にも大きな負担となります。
特に初めての青色申告では、記帳のルールや書類の保存方法に不慣れなため、こうしたミスが起きやすいです。
e-Taxの操作や複式簿記の理解が必要
65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿付けとe-Taxによる申告が条件となります。
複式簿記とは、すべての取引を「借方」「貸方」の2つの視点で記録する方法で、会計知識がない人にとっては難易度が高くなります。
また、e-Taxを使うにはマイナンバーカードの取得やICカードリーダー、パソコンの設定などが必要です。
これらの環境を自力で整えるには事前の準備が必要であり、手間がかかる上にトラブルが起きた時の対応も自分で行わなければなりません。
時間的な余裕がないと申告に間に合わない
確定申告の期限は通常、毎年3月15日までと決まっています。
青色申告に必要な作業は、1年分の帳簿作成、決算書の作成、確定申告書の作成と多岐にわたります。
仕事が忙しい人や副業で帳簿を管理している人にとっては、直前になって慌てるケースも少なくありません。
期限までに準備が間に合わなければ白色申告扱いとなり、控除も適用されなくなってしまいます。
手間とストレスが予想以上に大きい
自力での青色申告は、やり方を覚えれば不可能ではありませんが、最初の年は学ぶことが多く手間も相当かかります。
記帳のルール、税制改正、控除の適用条件、記載ミスへの対処など多くの知識を短期間で習得しなければなりません。
また、数字や法律に苦手意識がある人にとっては、申告作業そのものが大きなストレスになります。
自力でするのはコスト削減と天秤にかけて検討を
青色申告を自力で行うことは可能ですが「帳簿の精度・期限・税制知識・作業量・ストレス」などを含めて考えると決して簡単とは言えません。
会計ソフトの導入や、必要に応じて税理士への部分依頼も含め、費用対効果で判断する必要があります。
「節税したい」という気持ちだけで突き進まず、「控除を受けるための正確さ」を意識して判断しましょう。
青色申告のメリットとデメリット
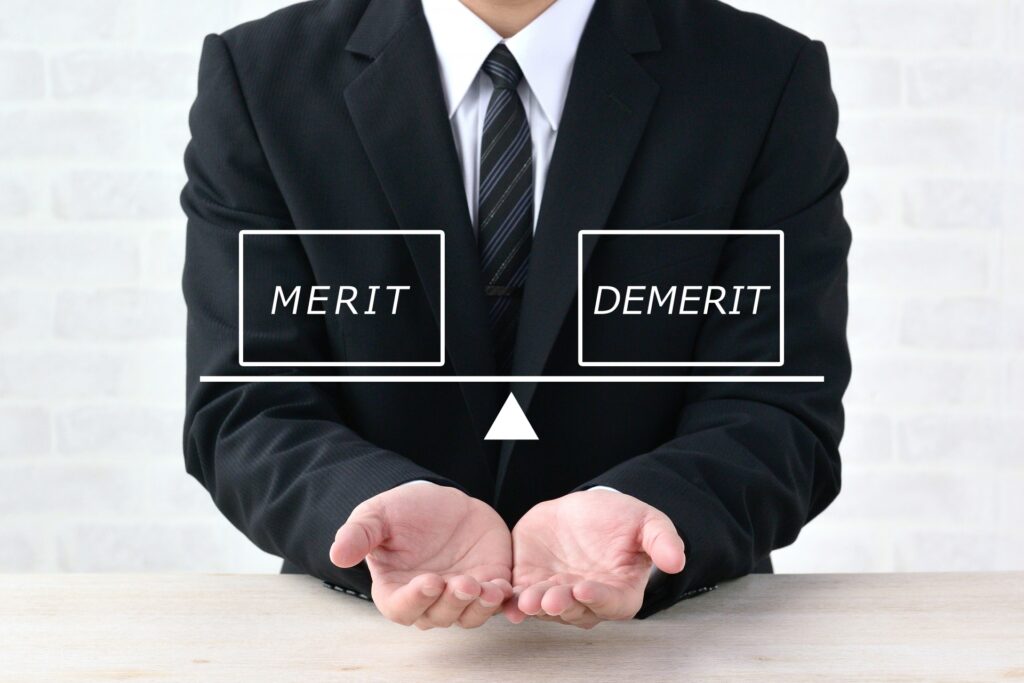
青色申告にはさまざまなメリットがある一方で、帳簿の作成や事前申請などの手間がかかります。ここでは、青色申告のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告の最大の魅力は、65万円もの特別控除を受けられる点です。
この控除額は事業所得から差し引くことができるため、課税対象の金額が大きく減り、所得税・住民税の負担が大幅に軽くなります。
控除を受けるには、e-Taxでの申告、または電子帳簿保存などの条件が必要です。
紙での提出や簡易記帳のみでは10万円や55万円の控除にとどまるため、控除額を最大にしたい人は準備がカギになります。
赤字の繰越し・繰戻しができる
青色申告をしていると事業で出た赤字を翌年以降に繰り越したり、前年度にさかのぼって税金を還付してもらうことが可能です。
3年間の繰越が認められており、将来利益が出た際に相殺することで節税ができます。
これは白色申告にはない特典です。
開業当初はどうしても赤字になりがちですが、この制度があることで将来の利益に対する不安が和らぎます。
家族への給与を経費にできる「専従者給与」
家族に仕事を手伝ってもらっている場合、その給与を必要経費として計上できるのも青色申告のメリットです。
例えば、配偶者に毎月5万円支払っている場合、年間60万円が経費として扱われ、その分課税所得を減らすことができます。
ただし、事前に「専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があり、金額が常識の範囲内であること、実際に勤務している実態があることが条件です。
家族の協力を得ている事業者にとって、節税しながら家族に正当な報酬を支払える非常に有効な制度です。
少額減価償却資産の特例や貸倒引当金の活用
青色申告では、少額の設備や備品を一括で経費にできる特例があります。
1つの資産が30万円未満であれば、購入した年に全額を必要経費にできるというものです。
また、貸倒引当金も認められており、売掛金などが将来回収できなくなるリスクに備えて一定額をあらかじめ経費計上することが可能です。
例えば、パソコンやプリンターを購入した場合、本来は数年かけて減価償却しますが、この特例を使えばその年に全額を経費にできます。
事業の設備投資が多い人や、取引先との掛け取引が多い人にとっては非常に有利な制度です。
白色申告より手間がかかる
青色申告には数々のメリットがありますが、その反面、提出書類や帳簿の整備が求められるため白色申告と比べて事務作業が増えます。
複式簿記での帳簿記入や青色申告決算書の作成、帳簿の保存期間(7年間)など、やるべきことは決して少なくありません。
これまで確定申告に触れてこなかった人にとっては、最初は戸惑うかもしれませんが慣れてくると効率的に処理できるようになります。
手間はかかりますが、それを補って余りある節税効果があるのが青色申告の特徴です。
事前申請が必要(期限を逃すと適用不可)
青色申告を行うには「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
これを出していなければ、いくら帳簿を整えていても青色申告はできません。
この申請書は、原則として「その年の3月15日まで」に提出する必要があります。
新しく開業した場合は、開業日から2か月以内の提出が条件です。
もし期限を過ぎてしまった場合、その年は白色申告になり青色の特典は一切使えません。
この点を見落としている人が多く、後悔してしまうケースが多いため、青色申告を考えているならまずこの申請書の提出を最優先にしましょう。
初心者にはやや複雑?対処法やサポート手段
青色申告は、初めての人にとっては確かに複雑に見えるかもしれません。
ただ、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や民間の会計ソフトを使えば、案外スムーズに進められます。
また、税務署や商工会議所では無料相談も行っており、不明点があればプロに直接聞くことも可能です。
特に開業したばかりの人は、地域の「創業支援センター」などを活用すると安心です。
難しそうに感じてもツールやサポートを使いこなせば、自力での申告も十分可能です。
自力で青色申告する際の不安・疑問

「青色申告は税理士に頼むべき?」「会計ソフトは必要?」という疑問をお持ちの方も多いかと思います。ここでは、自力申告に向いている人の特徴や、申告方法ごとの違いをわかりやすく解説します。
税理士に頼んだほうがいいのはどんな人?
青色申告を自分でできるかどうかは個人の状況や知識レベルによって変わりますが、次のような方は税理士に任せた方が安全です。
- 収入が複数ある(副業、投資、不動産収入など)
- 高額な売上や経費が発生している
- 複式簿記に不安がある
- 忙しくて帳簿や申告に割く時間がない
国税庁の統計資料「申告所得税標本調査」によると、事業所得者のうち約2割が税理士などの専門家を活用しています。
特に所得が高くなればなるほど、誤りによるリスクが増えるため、専門家の手を借りるメリットが高まるという傾向があります。
もちろん自力での申告は可能ですが、税理士のサポートは大きな安心材料になります。
会計ソフトは必要?手書きでも可能?
青色申告は手書きでも可能ですが、特別控除(65万円や55万円)を受けるためには複式簿記で記帳することが条件です。
複式簿記は、仕訳帳や総勘定元帳に「借方・貸方」で記録を行う会計の基本形式で、慣れていない人には少しハードルが高いと感じるかもしれません。
会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで自動的に帳簿が生成され決算書も自動作成できます。
帳簿の正確性や効率を考えれば、手書きよりも会計ソフトの活用をおすすめします。
特に初めての青色申告なら、操作が簡単なクラウド型のソフトが最適です。
確定申告ソフトの使い勝手や手書きとの違い
確定申告書の作成は以下の3つの方法があります。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
- 市販またはクラウド型の会計ソフトを使う
- 全てを手書きで作成する
まず、国税庁の公式サービスは無料で利用でき、初心者でも項目に沿って入力するだけで申告書が作成できます。
しかし、簿記や仕訳には対応していないため、複式簿記での青色申告にフル対応しているわけではありません。
次に会計ソフトは、売上や経費の入力から青色申告決算書・確定申告書の作成、さらにはe-Tax連携まで一貫して行えます。
一方、手書きでの申告は、すべての帳簿と書類を自分で整え手計算で記入していく必要があります。
誤記や記入漏れのリスクが高く、控除を正しく受けられないケースもあるため相応の知識が必要です。
申告の精度と効率性を考えると、やはりソフトの導入は有利です。
中でもクラウド型はアップデートも自動で、税制改正にもすぐに対応できる点が大きな強みです。
自力でできる!青色申告の具体的なやり方

青色申告を自分で行う場合はどのような手順で進めていけばよいのでしょうか?ここでは、申請から帳簿作成、申告書提出までの流れなどについて詳しく解説します。
青色申告承認申請書を提出する(開始前に必要)
青色申告を始めるには、まず「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
この申請をしていないと帳簿をどれだけ整えても青色申告はできず、白色申告扱いとなってしまいます。
- 新たに開業した場合・・・開業日から2ヶ月以内
- 既に事業をしている場合・・・その年の3月15日まで
申請書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能でe-Tax経由でも提出できます。
最初のステップとしてこの申請は絶対に忘れてはいけないポイントです。
帳簿を準備・作成する
帳簿のつけ方には「簡易簿記」と「複式簿記」の2種類があります。
青色申告で10万円の控除を受けたいなら簡易簿記、55万円または65万円の控除を受けたいなら複式簿記が必須です。
簡易簿記は、現金の出入りを時系列に記録するシンプルな方法で仕訳帳や現金出納帳があれば足ります。
一方、複式簿記は借方・貸方の2方向で取引を記録し、帳簿の構造がやや複雑ですが利益構造を明確に把握できます。
記帳に必要な帳簿の種類(仕訳帳・元帳など)
青色申告で複式簿記を行う場合は以下の帳簿が必要です。
- 仕訳帳・・・すべての取引を日付順に記録
- 総勘定元帳・・・勘定科目ごとのまとめ
- 現金出納帳・・・現金の出入りを管理
- 預金出納帳・・・口座の出入りを記録
- 売掛帳・買掛帳・・・売上や仕入の掛け取引管理
- 固定資産台帳・・・設備などの資産管理
これらを正しく記入・保存することで申告時の信頼性が上がり、控除も確実に受けることができます。
おすすめの記帳方法(手書き・Excel・ソフト)
記帳方法にはいくつかの選択肢がありますが、クラウド型の会計ソフトを使うのが時間効率も精度も高くおすすめです。
- 手書き・・・自由度は高いが手間も多くミスしやすい
- Excel・・・無料で始められるが関数や仕訳の理解が必要
- 会計ソフト・・・初心者でも安心。自動仕訳・集計・提出連携まで対応
青色申告決算書と確定申告書の作成方法
確定申告書作成コーナー・会計ソフト・手書き
青色申告で必要な書類は以下の2つです。
- 青色申告決算書(損益計算書や貸借対照表を含む)
- 確定申告書B(第一表・第二表)
書類の提出方法(e-Tax・郵送・窓口)
書類の提出方法は以下の3つです。
- e-Tax(オンライン)
- 郵送
- 税務署の窓口に直接持参
e-Taxを利用することで控除が65万円まで増えるなどのメリットがあり、利用者も年々増えています。
マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば24時間いつでも申告が可能です。
それぞれの方法にメリットがありますが、申告ミスを減らしたい方にはe-Taxがもっとも便利です。
時間のない方や郵送準備が面倒な方にもおすすめです。
青色申告に必要な書類と提出期限
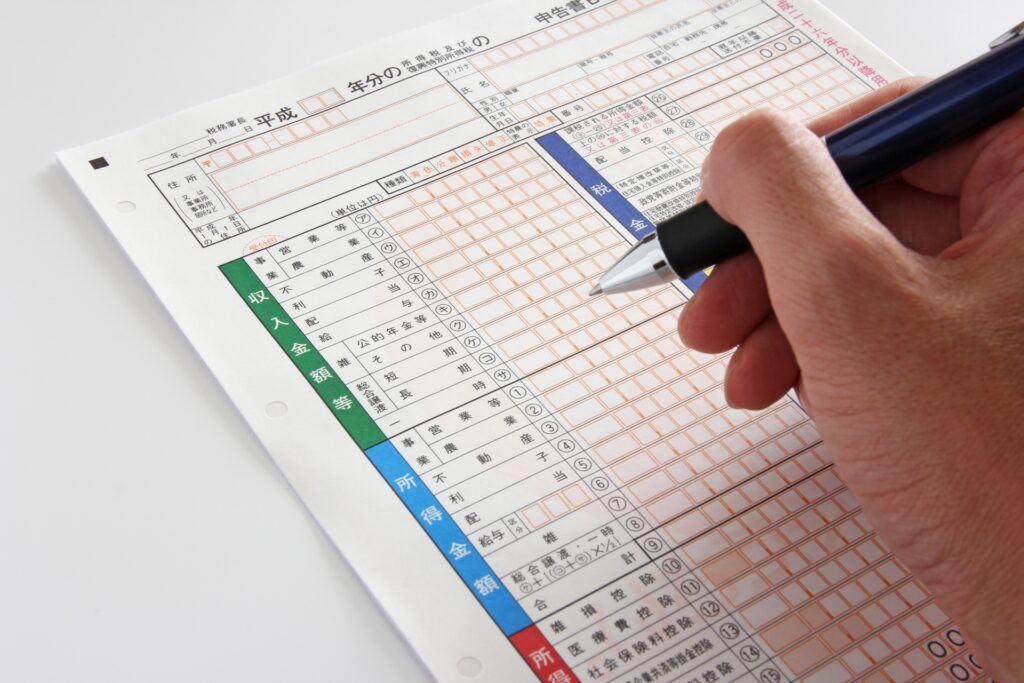
青色申告は提出期限を過ぎると控除が受けられないなどのリスクもあるため、必要書類と提出期限はしっかりと理解しておきましょう。
青色申告決算書
青色申告に必要な代表的な書類が「青色申告決算書」です。
これは1年間の事業の収入と支出をまとめた書類で、損益計算書と貸借対照表の2部構成になっています。
この書類は、どれだけ儲かったか(利益)や、どんな資産や負債があるかを税務署に示すために使われます。
複式簿記で65万円または55万円の特別控除を受けるにはこの決算書の提出が必須です。
国税庁の「確定申告特集ページ」にあるテンプレートや、会計ソフトを使えば自動で作成できる仕組みが整っているため、決して難しすぎる書類ではありません。
収支が明確に分かる書類を提出することで正しく節税できるだけでなく、金融機関の融資や家のローン審査にも有利に働く場合があります。
確定申告書(第一表・第二表)
確定申告書は、納税額を計算するために必要な正式な書類で「第一表」と「第二表」の2枚構成になっています。
第一表は、1年間の総所得額や各種控除額、税額を記入するメインの用紙で誰でも提出が必要な書類です。
第二表は、収入の内訳や控除の詳細を記載する補足資料で青色申告をする人には必須のものとなります。
この申告書も国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で簡単に作成でき、会計ソフトを使っていれば自動で生成されます。
この2つの申告書は税金を正しく計算するために最も重要な書類なので、記載内容の正確さが何よりも大切です。
控除の証明書類
青色申告では必要経費だけでなく、さまざまな「控除」が使えます。
その控除を受けるには証明書類の提出または添付が求められます。
主な控除と必要な書類の一例は以下のとおりです。
| 控除の種類 | 必要な照明書類例 |
|---|---|
| 社会保険料控除 | 国民年金や健康保険の支払証明書 |
| 生命保険料控除 | 保険会社から送られてくる控除証明書 |
| 医療費控除 | 領収書の明細、医療費通知書など |
| 寄付金控除(ふるさと納税など) | 寄附受領証明書やワンストップ特例未利用時の証明書 |
医療費控除などは金額が大きくなりやすく、準備が甘いと控除を受けられないことがあります。
年間10万円以上の医療費を支払った場合などは、レシートの整理と記録を日頃から行っておきましょう。
証明書類は後から準備しようと思っていると紛失することがあるため、日々の整理が大切です。
申請期限と提出期限(守らないと白色扱いに)
青色申告を行う上で最も注意が必要なのが「期限」です。
書類をいくら完璧に整えても提出期限を過ぎてしまえば、それだけで青色申告が認められず白色申告に格下げされてしまいます。
| 項目 | 提出期限 |
|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内、または3月15日(既存事業者) |
| 青色申告決算書・確定申告書(所得税) | 毎年3月15日まで(原則) |
これらは「1日でも遅れるとアウト」とされており、税務署も容赦なく白色申告扱いに変更します。
期限を守ることは内容の正確さ以上に重要な要素です。
特に初めて申告する方はスケジュールを逆算して準備を始めましょう。
青色申告でよくある失敗と注意点

申請期限を逃したり帳簿の記入ミスをしたりすると、せっかくの青色申告のメリットが受けられなくなります。ここでは、実際によくある失敗例とその対処法などについて詳しく解説します。
申請期限を過ぎてしまった場合の対応
万が一、青色申告承認申請や確定申告の期限を過ぎてしまった場合、その年は原則として青色申告ができません。
白色申告として扱われ、特別控除や赤字の繰越など多くのメリットを受けられなくなります。
ただし、翌年以降に再度「青色申告承認申請書」を提出すれば、再び青色申告へ移行することが可能です。
いったん期限を過ぎた場合の取り戻しはできないため、最初の年度こそ注意が必要です。
2年連続で期限後申告するとどうなる?
2年連続で期限後申告をすると「青色申告承認の取消し対象」になることがあります。
「申請はしたが提出が毎年遅れている」という場合、制度の適用そのものを取り消される可能性があるのです。
これは国税庁が公表している「青色申告の取消事例集」でも明記されています。
納税者側のミスとはいえ厳格な運用がされている点は見逃せません。
提出期日の厳守は制度の継続利用においても非常に重要です。
帳簿付けのミスによる控除取り消しリスク
青色申告は帳簿の正確性が重視される制度です。
帳簿の不備やミスがあった場合、たとえ提出期限を守っていても控除が受けられないことがあります。
よくあるミスには以下のようなものがあります。
- 領収書の紛失
- 仕訳ミス(借方・貸方の逆)
- 金額の計算違い
- 二重計上や未計上
帳簿が正確に作られていないと税務署に判断されると「控除額の減額」や「訂正申告の指導」などの対象になります。
記帳の基本を正しく理解し、できれば定期的に見直すことでこうしたリスクは回避できます。
自宅やプライベートの支出を経費にしてしまう誤り
よくある失敗の一つに、「プライベートな支出を事業経費として計上してしまう」ミスがあります。
これは「家事関連費」と呼ばれ、必要経費に算入できるものとできないものの判断が重要です。
例としては以下のような支出です。
| 支出例 | 経費にできる? |
|---|---|
| 自宅の家賃 | 一部のみ(按分計算が必要) |
| 個人のスマホ代 | 事業利用分のみ(通話明細など必要) |
| 家族での飲食代 | 原則不可(接待交際費なら条件付き可) |
これらの支出をすべて経費にしてしまうと、税務調査で否認される可能性があり追徴課税を受ける恐れがあります。
家事関連費はグレーゾーンが多いため、必ず按分や使用実態に基づいた記録を残すことが大切です。
必要経費にできない支出の線引き方法
必要経費として認められる支出と、そうでない支出の判断も非常に重要です。
基本的なポイントは「その支出が事業の収益に直接つながっているかどうか」です。
- 生活用品(食費・衣類・日用品)
- 家族旅行や娯楽費
- 個人の保険料(業務関連でない場合)
逆に、事業に必要な備品購入や出張交通費などは明確な領収書があれば経費として計上できます。
支出の判断がつかない場合は、以下のように対応すると安全です。
- 用途を帳簿にメモする
- 按分(何割が事業用か)を記録する
- グレーなものは税理士か税務署に相談する
線引きが曖昧な支出は後からトラブルになりやすいため「本当に業務に必要だったか」を常に意識することが、青色申告の精度を高めるポイントです。
会計ソフトなしでも青色申告できる?

青色申告は必ず会計ソフトが必要というわけではありません。ただし、控除額や作業負担には違いがあるため、自分のスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
会計ソフトなしの記帳例(現金出納帳・預金通帳)
会計ソフトを使わなくても青色申告の記帳は可能です。
実際に多くの個人事業主や副業会社員が、エクセルやノートを使って記帳を行っています。
青色申告では現金の出入りや口座の動きを記録する帳簿が必要なため、最低限、以下の2つは用意しましょう。
- 現金出納帳・・・現金の収入・支出を日付順に記録
- 預金出納帳・・・銀行口座の入出金を記録(通帳コピーを貼るのも可)
例えば、現金で仕入れをしたら「支出」として記入し、レシートを添付して保存。
振込で報酬が入金されたら「収入」として記録し、該当する通帳のページを印刷しておくと良いでしょう。
現金管理は後からまとめて処理するとミスが起こりやすいため、毎日または週ごとの記帳がおすすめです。
簡易記帳で10万円控除を受ける方法
複式簿記に比べて簡単な「簡易簿記」であれば、会計ソフトなしでも十分対応できます。
簡易簿記とは、現金出納帳や売上帳、経費帳などを使って日々の取引を1つずつ記録していく方法です。
取引の記録方法は片方の勘定科目だけで済むため、会計の知識が浅くても対応しやすいです。
例えば、以下のような帳簿で対応できます。
| 帳簿の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 売上帳 | 商品・サービスの販売金額や日付 |
| 経費帳 | 支払った仕入代、交通費、通信費など |
| 現金出納帳 | 現金の入出金記録 |
| 預金出納帳 | 通帳を元にした記録 |
正確に帳簿がつけられており保存義務を守っていれば、10万円控除の適用対象になります。
65万円控除を目指すならソフト導入が有利
より大きな控除額である65万円控除を受けるには、「複式簿記」での帳簿記入とe-Taxによる提出が必須条件です。
複式簿記は取引を「借方」「貸方」で同時に記録する必要があるため、手書きではかなりの知識と手間を要します。
そのため、税務署も複式簿記を行う際には会計ソフトの利用を推奨しています。
手書きだとミスや転記漏れが起こりやすく控除の取消リスクもあるため、65万円控除を確実に得たい人は最初からソフトを活用する方が賢明です。
ソフト導入なしで青色申告するためのチェックポイント
会計ソフトを使わずに青色申告を完了させたい場合は、以下の5つのポイントを必ず押さえておきましょう。
- 青色申告承認申請書を事前に提出しているか(期限厳守)
- 必要な帳簿をすべてそろえているか
- 現金・預金・売上・経費をもれなく記帳しているか
- 記帳内容に数字の整合性や証拠書類(レシート等)があるか
- 申告期限内に書類提出ができる体制かどうか
これらを全て満たしていれば、ソフトなしでも10万円控除を受けて問題なく申告可能です。
ただし、65万円控除を狙う場合は、会計知識がある程度ある人でないと現実的に厳しいケースが多くなります。
まずは10万円控除を目指し、必要があれば次年度からソフト導入を検討するというステップもおすすめです。
青色申告に便利なサービス・おすすめツール

青色申告をスムーズに進めるためには、会計ソフトやスマホアプリ、税理士サービスなどを活用するのが効果的です。最後に、青色申告に便利なサービスやツールをご紹介します。
初心者向け会計ソフトの比較
青色申告初心者に人気があるのは、次の3つのクラウド会計ソフトです。
| サービス名 | 特徴 | 月額料金(税込) |
|---|---|---|
| freee(フリー) | 操作が直感的、スマホ対応◎ | 約1,628円~ |
| マネーフォワードクラウド | 確定申告に強い、帳簿も自動作成 | 約1,078円~ |
| 弥生会計オンライン | 初年度無料あり、サポート充実 | 約1,320円~ |
これらはすべて「複式簿記」「仕訳の自動化」「e-Tax対応」といった機能を搭載しており、青色申告65万円控除にも対応しています。
どれも無料お試し期間があるため、まずは実際に触ってみて操作感を確かめてみるのがおすすめです。
スマホで完結する確定申告アプリの活用
最近では、スマホだけで青色申告の作業を完結できるアプリも登場しています。
freeeやマネーフォワードは、スマホ専用アプリからレシートの読み取りや取引の記帳ができ、出先でも簡単に処理が進められます。
スマホカメラでレシートを撮影すると自動で勘定科目を判別して記帳、データはクラウド上に保存されるためパソコンとの連携もスムーズです。
普段からスマホを使い慣れている方にとっては、非常に便利なツールとなるでしょう。
税務署・商工会議所など相談できる公的窓口
会計ソフトなしで進める場合、わからないことが出てくるのは当然です。
そんな時は、以下のような公的な相談窓口を活用しましょう。
- 税務署の確定申告相談窓口(申告時期は混雑するので早めの相談が吉)
- 商工会・商工会議所の記帳指導(無料~数千円で指導)
- 青色申告会(有料だが細かくサポートしてくれる)
これらの機関では帳簿の付け方や記入ミスのチェック、申告書の作成方法など実務的なアドバイスが得られます。
初心者や不安のある方は、どこかの窓口を一度は利用しておくと安心です。
丸投げできる税理士サービスの特徴と料金目安
どうしても自力での申告が難しい場合は、税理士への依頼も一つの選択肢です。
特に複式簿記や65万円控除を狙う人には、プロのサポートが効果的です。
料金相場は事業規模にもよりますが、青色申告のみであれば年間5万円~10万円ほどです。
記帳代行まで依頼するともう少し高額になりますが、節税や時間の節約を考えれば十分に価値があります。
最終的には、記帳の手間や時間、ミスのリスク、費用対効果を考慮して、自力か外注かを判断するのが理想的です。
今回は、青色申告は自力でできる?という疑問に関して詳しく解説してきました。青色申告は正しく行えば非常に大きな節税効果が期待できます。しかしその一方で、記帳ミスや提出期限の遅れ、経費計上の間違いなどによって大きな損をしてしまうリスクもあります。特に65万円控除の場合は、複式簿記やe-Tax対応など、一定の会計知識と適切な準備も必要になってきます。専門家のサポートにはある程度の費用が発生しますが、安心感と正確性が大きく向上します。当事務所では、税務関係や会計処理はもちろん、節税方法や経営に関するアドバイスなどあらゆる事に対応しております。初めての青色申告に不安を感じている方、帳簿管理や節税対策、事業の経営に関して不安のある方は、無料相談も行っている当事務所へ是非お気軽にご相談ください。

Hey! This is my first visit to your blog!
We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the
same niche. Your blog provided us valuable information to work
on. You have done a extraordinary job!